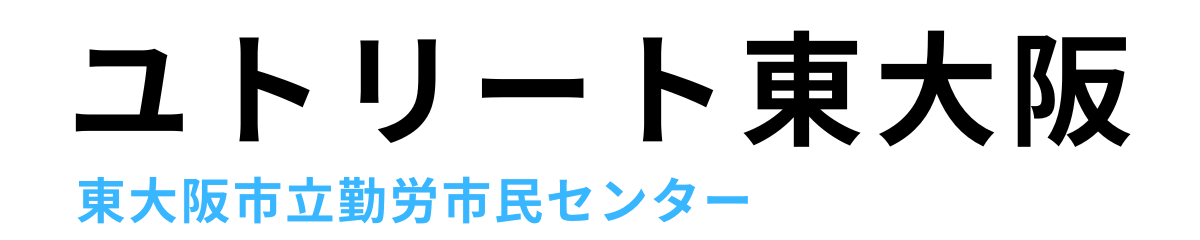前回のコラムではパワハラの定義を振り返りましたが、近年では「逆パワハラ」という問題も注目されています。逆パワハラも通常のパワハラと同様に、以下の3要素を満たす場合に問題視されます。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
この「優越的な関係」という点が、逆パワハラでは逆転しています。つまり、部下や同僚など、本来なら上司よりも立場が下とされる側から、上司への言動として現れるケースです。
どんな時に「逆転」が起こりうるのか?
通常、上司は業務命令や監督・指導を行う立場にあり、「優越的な関係」にあるのは上司側です。
一方で、逆パワハラでは部下が一定の力を持つことで、実質的に上司より優位な立場となり、ハラスメントに及ぶケースが問題となります。
例えば、以下のような場面が挙げられます。
【例1】
スマートフォンなどのデジタル機器に不慣れな上司が部下に操作方法を尋ねた際、部下が
「そんなことも分からないんですか?小学生でもできますよ。できないなら、もう触らないでください」
といった嘲笑的・侮蔑的な態度をとる。
このように、部下が知識やスキル面での優位性を背景に、精神的な圧力を与えるような言動は、逆パワハラに該当する可能性があります。
【例2】
部下が業務上の注意を受けた際に、「それ、パワハラですよね?今録音したので、訴えることもできますよ」などと、正当な指導を一方的に「パワハラ」と決めつけて、上司に対し威圧的な言動をとるケース。
このように、「パワハラ」の概念を盾に、指導を封じようとする行為は、逆パワハラに該当する可能性があります。
パワハラは誰にでも起こりうるもの
パワハラは「上司から部下」だけでなく、部下が上司に精神的な苦痛を与える「逆パワハラ」という形でも起こり得ます。
立場や肩書にかかわらず、一時的にでも優位な状況に立てば、誰もが加害者にも被害者にもなりうるのです。
パワハラを防ぐためには
- 相手の立場や受け止め方に配慮する。
- 指導とハラスメントの線引きを意識する。
- 必要に応じて第三者の視点を取り入れる。
といった姿勢を日頃から意識することが大切です。
「自分も加害者になるかもしれない」という意識こそが、ハラスメントのない職場づくりの第一歩です。